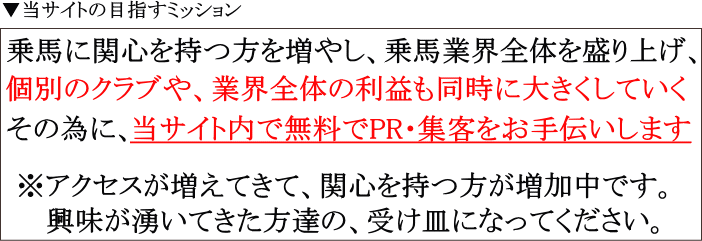
爽快乗馬を運営しているハタノと申します。
私自身が乗馬が好きで、複数の乗馬クラブで習っていた経験から、だんだんと乗馬業界そのものに興味を持ち始めました。
前提知識があって始めて見える事、知識が邪魔して盲点を作り出してしまう事、どちらもあると思いますが、クラブで習っていた立場の為、業界内からではなく、業界の外側から眺める事が出来たおかげで、先入観がありませんでした。
良いところも、そうでないところも含め、多くの疑問や問題点が見え始め、これなら問題解決に貢献出来るのではないかと、考えるようになっていきました。
そして「乗馬に関わる業界そのものを盛り上げたい」と、当サイトを立ち上げました。
小さな広告費を稼ぐ、小さな自己利益が目的ではありません。
そんな小さな一個人の事ではなく、
「業界全体を盛り上げながら、個別のクラブや業界全体の利益も同時に大きくしていく」という枠で考えています。
15年以上ウェブマーケティング、HP作成、広告運用を行ってきた経験が、ここに生かせるという考えから行動を起こしました。
正直、私に金銭的な利益があるかと言えば、答えはNOです。
どちらかと言えば持ち出しが多くなるので、利益的にはマイナスという方が、正確な表現になるかと思います。
「自分の金銭的な利益にならないのに、何故やるのか?」
これについては、明確な理由がありますが、順を追って後ほど詳しく明記します。
最終到達目標
「乗馬に関心を持つ方が増え、業界全体が盛り上がり、業界全体の利益も同時に大きくしていく」事が、目指すところになります。
その為には、大きく分けると以下の2つが、必須になってくると考えています。
1、乗馬に関心を持つ方を増やす事が最も重要
2、乗馬というサービスを提供する方が集客に悩まず、サービス提供に専念出来る環境を構築し、サービスに係るスタッフの待遇改善(昭和思考からの脱却)
この2つについて、もう少し詳しく書いていきます。
乗馬に関心を持つ方を増やす道筋
残念ながら、趣味や習い事を含め、乗馬は一般的ではなく身近な存在ではありません。
もちろん地域差はありますが、普段の生活の中に存在していないので、そもそも触れる機会がありません。最も身近なのがTVで放送もされている、競馬というのが現状かと思われます。
この為、まず選択肢に上がるように、「乗馬を身近に感じてもらう」必要があります。
ずいぶん前からキーになりそうなのが、漫画・アニメ・ドラマのようなコンテンツから知ってもらうというルートだと考えていましたが、その後にウマ娘の登場により立証されたと思います。
身近に感じてもらう事が先決の為、直接的な効果がすぐ現れなくとも、継続していく必要があると考えています。
直球勝負というよりは、間接的に広げていくイメージです。
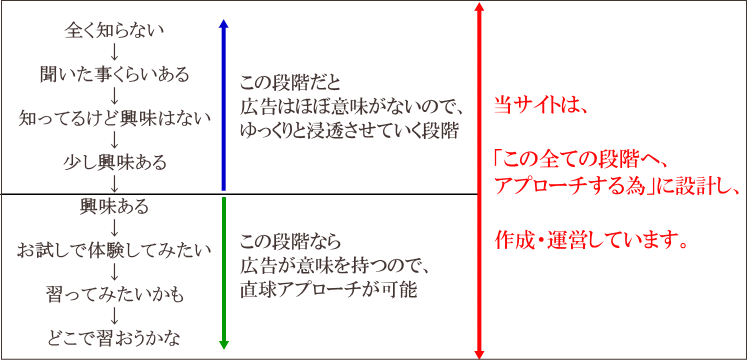
当サイトでも、キングダム等の戦国系への憧れに焦点を当てたり、全国の馬が登場する祭り等にも焦点を当て、乗馬に触れる機会を広げていく等も、間接的なイメージの範囲です。
すでに結果は出てきていて、まだ私が描いている完成形の10%もHPは完成していませんが、既に2300ページを超え、ますます増えていきます。
集客に悩まずサービス提供に専念出来る環境を構築
集客(プロモーション)が、最も大きなネックとなっているところは、多いのではないかと推察します。
Youtubeに上がっている、撮影のプロが作成した紹介(PR)動画も見かけますが、確かにプロが作成しただけあって、綺麗な映像に仕上がっていると思います。
ただし、「綺麗なだけ」という印象を受けます。
作成を依頼した側からすれば、綺麗なカッコイイ動画が出来上がれば、凄いという印象を受けるでしょう。しかし、それは制作側から依頼者への話にすぎません。
動画を届ける相手(お客さん)に、どのような目的で見てもらいたいのでしょうか?
最も重要な「動画の目的」が、すっぽり抜けているような気がしてなりません。
ホームページ制作でも同じですが、webデザイナーやHP制作会社に依頼しても、制作は専門であっても、集客に強いとは限りません。
結論から言えば、
「綺麗なだけの映像では、集客は出来ません」
「綺麗なだけのHPでは、集客は出来ません」
「集客を目的に制作するから、集客が出来る」という、当サイトでも繰り返し主張しているように、何がしたいのかという目的が最も重要で、ここの視点が抜けていれば、得たい結果が得られるはずがありません。
例えば、集客用の動画にしても
「体験乗馬がしたい方へ向けた動画」
「乗馬を習いたい方へ向けた動画」
「スキルアップがしたい中・上級者へ向けた動画」
目的に応じて伝える内容が全く違うので、別動画にするべきところを、ごちゃまぜにして一つの動画にしてしまうから、話の焦点がボケてしまい、結果何も伝わらない綺麗なだけの動画が出来上がってしまうのです。
飲食店のように、誰かが料理の写真を口コミサイトやSNSに上げ、口コミなどの情報を読む事が出来たりするものと違い、乗馬クラブの情報はwebから入手するのが非常に困難です。
せっかく乗馬に興味を持ってくれた方がいても、乗馬クラブの場所や中身について、情報がほとんど手に入らないという事は、
1、まず見つけてさえもらえていない
2、運よく見つけてもらっても、情報が不足しすぎている
2については「人間は基本的に、よく分からない、理解出来ないものにはNOと言う」行動を取るので、非常にもったいないです。
HPの中身についても、乗馬クラブの顔が見えないものがほとんどで、どこも同じような事しか記載がなく、他とどう違うのかがまったく分かりません。
例えば、「うちは馬との触れ合いを最も大事にしている」「うちは競技志向の方に技術を教えるのが得意」等、必ず特色があるはずですが、ほとんど情報がありません。
Youtubeの動画を見ていても、馬場で誰かが馬に乗っているようなものがほとんどで、これだと他クラブとの差別化が出来ないので、ここに行ってみようという動機が生まれません。
「何故ここに行こうと思うのか」
「何故ここでなければいけないのか」という理由付けがありません。
どこも同じに見えるなら、近いところか安いところしか選ばれません。
この結果、何が起こるかというと、お客さんが求めるものと、クラブが提供するものとミスマッチが生まれ、嫌になり辞めてしまう事になります。
SNSの誤解
広告等を扱った経験がない方だと、SNSで情報発信をしようという発想になりがちです。
SNSがどういうものであるかも知らずに、ただ何かを上げても、誰も見ません。せいぜい仲間内(身内)が確認する程度で終わります。
どうして見てもらえないんだろう?投稿を増やせば、そのうち見てもらえると考えて、やってみるけど状況は変わらない。何故だろう?で、面倒になり更新停止。
ほぼほぼ、この流れに落ち着きます。
こうなる理由は簡単です。SNSは現在の興味関心、過去の興味関心を分析し、その興味関心の中に閉じ込める事が目的だからです。
SNSは「エコーチェンバー現象(情報、信念などが閉じたコミュニティ内で反復されることで増幅、強化される現象の事)」を引き起こす仕様になっています。
最初から過去や現在で興味関心の対象になっていなければ、その人が見る空間には存在する事がないのです。
戦略を持たずに取り組んでも、狙った結果が出るはずがありません。これが全てです。
当サイトからの提案
ただ紹介するページを作っても、何故このクラブを選ぶのかという動機付けが弱すぎて、紹介コンテンツとして非常につまらないものとなってしまいます。
そこで当サイトからの提案で、
インタビューに伺わせていただき、紹介動画(インタビューとインサート)を無料で作成し、インタビューを元にテキストによる解説を加え、当サイトで紹介をしたいと考えています。
動画にする理由は、言葉だけでは伝えられない“非言語“の部分があるからです。
笑顔であったり、話のトーンであったり、雰囲気であったり、“非言語“の部分が非常に重要なので、話すのが上手い下手は関係ありません。
堅苦しく長いだけの動画を作成しても無意味な為、クラブの紹介動画では最も大事にしている事に特化し、ラフにクラブの特色(カラー)を語っていただければと思います。
それならば「自分で撮影すれば良いんじゃないの?」と思うかもしれませんが、大きな勘違いです。それだと自分が発信したいだけの情報発信になってしまう可能性が高いです。
インタビューは、インタビュアーの存在が重要になってきます。用意した台本を読み上げるだけじゃ、“非言語“の部分がしっかりと伝わりません。
ニュースキャスターが読み上げる、ニュースをイメージすれば、分かっていただけると思います。
体験乗馬を行っているのであれば、こちらは別動画で内容を特化させて作成し、インタビューを元にテキストによる解説を加え、当サイトで紹介します。
ただし、「紹介する上で重要な条件」があります。
それは、「馬・お客さん・スタッフの全てを大事にしている事」です。
ここをクリア出来ないところは、紹介する事が出来ません。
もちろん、受け取り手が判断する事なので、完璧に出来ているかどうかではなく、クラブとして全員が共有出来ているかどうかです。
昭和思考からの脱却提案
金儲け至上主義で、お客さんをATMとしてしか扱っていないところや、馬はただの道具、スタッフは奴隷扱いみたいな場所は、実際に存在しているのが現状です。
すでに昭和から元号が2回も変わっているのに、未だに昭和の思考が停止する根性論スタイルのままのところが、多く存在しています。
その最たる例が、「入会金」の存在です。
意味があって導入しているのなら、何も問題はありません。うちは格式を重んじるから、敷居を設けているんだ、こういう理由付けがされているなら問題ありません。
ところが、「他クラブへ移動しにくくする為」「昔からやってるから(思考停止の慣習)」等が理由であるならば、いつまで昭和の世界観の中にいるのですか?と、大きく疑問に感じます。
業界外から見ていると、すごく閉鎖された空間で、時間が昭和のまま止まっているように感じます。
昭和思考が強いところだと、強引な営業スタイル等で、お客さんが嫌な思いをしてしまい、乗馬を辞めてしまうケースも少なくありません。
乗馬が嫌いなのではなく、乗馬クラブで嫌な思いをさせられたのが原因で辞めた場合、多くのケースで二度と乗馬業界へ戻ってきません。
せっかく乗馬に興味を持って入ってきてくれた方が、こんな事が理由で辞めてしまうのは、業界全体の首を絞め続けているだけです。
だからこそ「馬・お客さん・スタッフの全てを大事にしている事」が最重要で、ここをクリア出来ないところは紹介したくないのです。
サービスに係るスタッフの待遇改善
これは「馬・お客さん・スタッフの全てを大事にしている事」にも直結している部分で、スタッフを大切にしていないところは、そのシワ寄せが馬にいき、そしてお客さんへ到達します。
問題の本質は、経営の設定の失敗と、昭和の思考が停止する根性論スタイルの2つだと考えられます。
経営の設定の失敗は、馬の頭数、スタッフの数、開催可能な最大レッスンと参加可能なお客さんの数を考えれば、売上げの最大値は計算可能です。
ここからどの程度まで、レッスンの数が少なくても経営が成り立つかは、当然に把握出来るので、ここの設定が間違っていれば、無理やり何か方法を考えて、売上げを上げなければならない状態になります。
最も簡単で思考が要らないのが、経費の削減です。
スタッフを減らし、一人あたりの業務負荷を上げれば、経費は削減出来ますが、スタッフは疲弊し離職率が上がり、質がどんどん低下します。
これが典型的な、昭和の思考が停止する根性論スタイルです。
これが馬の管理に響いていき、最終的にお客さんへのサービスの低下を招き、売上げの低迷に繋がっていきジ・エンドです。
経営の設定の失敗は根が深いので改善は大変ですが、単純に集客が上手くいっていない状態であれば、状況にもよりますが改善の余地はあるかと思います。
乗馬業界を取り巻く現在の状況
業界だけを見ても無意味なので、もう少し大きな日本という単位で、状況をみていきます。
国際通貨基金(IMF)の最新予測では、2025年の日本の名目国内総生産(GDP)は、ドルベースでインドに抜かれ、世界第5位に転落する予測です。
そして、一人あたりGDPも韓国・台湾に抜かれて38位になっている状況です。
さらに、2024年の死亡数から出生数を引いた人口は、約90万人の減少となりました。2025年は、さらに減少数が増加する予測です。
残念ながら、今のところ日本の経済が復活する要素はありません。人口が減り続け、経済が真下を向いている状態で、生活に余裕がなくなれば、削られる対象は決まってきます。
乗馬クラブのように商圏が限られている業種では、人口減少の影響は甚大です。
自分の金銭的な利益にならないのに、何故やるのか?
「乗馬に関わる業界そのものを盛り上げたい」という思いから、当サイトを立ち上げました。
そして、業界全体を盛り上げる為には、何が必要かと考え続けた時に、乗馬に興味を持つ人を増やすだけでは足りないのではないか、という問いが生まれました。
実際に乗馬クラブに行くと、場所にもよりますが、歴史があると言えば聞こえは良いですが、更衣室やシャワールーム、トイレ等が随分と年季の入った場所が多いなという印象を受けました。
通っている身であっても、これでは若い方はまず通う気にならないな、そう強く感じる場所もあります。年季の入った旅館等も、やはり若い方には選ばれません。
これを改善していくには、乗馬クラブが潤っている必要があると考え、業界全体を盛り上げると同時に、業界全体の利益も同時に大きくしていく必要があるのではないか、との結論に至りました。
「集客に悩まずサービス提供に専念出来る環境を構築」するという目標達成の為には、最初から自分が利益を生むビジネスとして展開するのは、本末転倒に感じます。
誰に向けたものなのか、意図が分からない動画やHP制作にお金を払うくらいなら、ちゃんと意図を持って制作しますよと営業すれば、それなりに利益を生む事は可能です。
しかし、そんな程度の小さな利益の為に、わざわざ自分の生命時間を使って、取り組む必要はないと考えています。
業界全体の変革を提言するからには、まずは乗馬クラブに利益がもたらされるようにしなければ、嘘になってしまいます。
そもそもとして、各乗馬クラブが乗馬に興味をもってもらう為に、面白さ等を伝えていくには限界があると感じます。
乗馬に興味を持つ人を増やして広げていくのは、各乗馬クラブが担う仕事とも思えません。
可能なのであればやった方が良いですが、クラブ運営の方が忙しいはずですし、興味を持った人に対し、どんな乗馬クラブなのかをアピールする事が、経営的にも本来やるべき最重要ポイントのはずです。
乗馬という業界に興味をもってもらう仕事は、別のところが担うべきだと思います。
15年以上ウェブマーケティング、HP作成、広告運用を行ってきた経験が、ここに生かせるという考えから行動を起こしました。
「乗馬を通じ、より多くの方に、より良い人生を送ってもらいたい」
そして、目的を「ビジネス」に限定してしまうと、せっかく良いものであっても、広がりに制限がかかってしまう。これが、明確な理由になります。
乗馬業界が外へ広がっていかない要因
もう随分前の事になりますが、当サイトを立ち上げようと内容を思案していた際に、乗馬クラブ関係者と話をする機会がありました。
そこで言われた言葉の中に、業界の闇を見た気がします。
ニュアンスとしては、「どれだけ馬の事を知っているというんだ?」「どれだけ上手く馬に乗れるというんだ」という、自分の知識や技術をベースとしたマウンティングです。
運営側(指導員も含む)が、こういう思考レベルなのであれば、クラブ内の雰囲気も最悪な状態だと思います。
ちょっと上手く乗れる、少し経験があるという、低レベルなマウントの取り合いが、まともな人達を遠ざけます。ベテランが幅を利かせる、昔の体育会系の部活のようです。
これでは、外へ広げていくという思考も働かず、当然アイデアも生まれません。
かの有名なアルベルト・アインシュタインの名言で、
「問題は発生したのと同じ次元では解決出来ない」というものがありますが、まさにこれが必要とされる思考です。
※正面から見ると1本の木
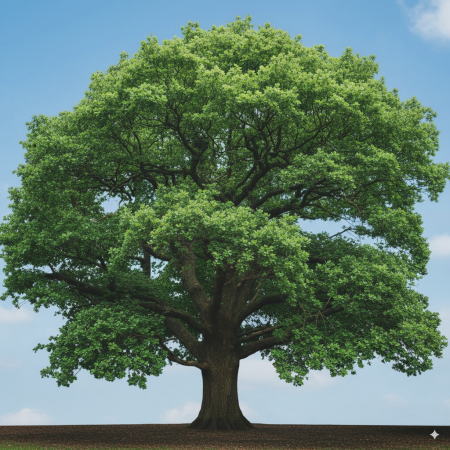
※角度を変えると、後ろには沢山の木が並んでいる

乗馬業界を取り巻く未来展望
ありとあらゆるものにAIが関わってくるのは、避けようがない世界であり、すでにAIの時代に突入し、急速に広がりつつ発展し続けています。
どんどんAIやVRに置き換わっていく中で、「リアルな体験の価値」は間違いなく上がっていきます。
テクノロジーによって、バーチャルな体験は圧倒的にコストが下がりますが、同時に圧倒的にコストがかかるアナログな実体験は、希少価値を生んでいきます。
豪華列車の旅が大人気すぎ、高額にも関わらず予約が取れない状態が、その良い例だと思います。
音楽や絵画等を現地へ行き、実際に自分の五感で感じるように、今後の未来においては「乗馬というリアルな体験」は、ほぼ間違いなく価値が上がっていくと予想されます。
※現在、都内へ移住した為、移動は電車になります。
